「人間」の時代の到来とその終焉の予言 -フーコー『言葉と物』より
前回の記事で書いた、アダム・スミスの労働価値説について、フーコーが『言葉と物』のなかで興味深い指摘をしている。よく知られているように、フーコーは『言葉と物』のなかでルネッサンス以降の西洋の知の枠組み(エピステーメー)の変遷を描いてみせた。すなわち、①16世紀のルネサンス時代における「類似」というエピステーメー、②17世紀から18世紀の古典主義時代における「表象」というエピステーメー、③19世紀以降の近代における「人間」というエピステーメー、という変遷である。

- 作者: ミシェル・フーコー,Michel Foucault,渡辺一民,佐々木明
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1974/06/07
- メディア: 単行本
- 購入: 5人 クリック: 55回
- この商品を含むブログ (148件) を見る
このうちで、アダム・スミスの労働価値説は「表象」のエピステーメーから「人間」のエピステーメーへの転換点に立っているというのがフーコーの解釈である。古典主義時代のエピステーメーにおける「富の分析」にはまだ〈生産〉という概念が登場しておらず、近代的な「経済学」は誕生していなかった。17世紀から18世紀にかけての「富の分析」のなかで焦点が当てられていたのは〈交換〉の機能であった。
16世紀のルネサンス時代においては、富は「貨幣の内在的価値」という観点から分析されていた。(美しい貴金属はそれ自体として富の標識であり、その輝きは「世界のあらゆる富の可視的外徴」であると考えられていた。)これが17世紀になると、貨幣は「富を表象し分析するための道具」となる。貨幣と富の相互的関係が、流通と交換という形態のもとに設定され、富と貨幣を同一視する重商主義が台頭してくる。
「たぶん、重商主義にとっては、貨幣が、可能なかぎりあらゆる富を表象する力をもち、それを分析し表象する際の普遍的道具であり、富の全領域をくまなく覆っていたからであろう。あらゆる富は〈貨幣〉となることができ、こうしてそれは流通の場におかれる。」(『言葉と物』新潮社、196頁)
貨幣は「あらゆる富の表象」であるがゆえに最重要な富として扱われたのである。こうして見ると、初期重商主義である重金主義は「表象」のエピステーメーに属しながらも、いまだ金銀の内在的価値という「類似」のエピステーメーを引きずっているところがある。これに対し、後期重商主義である貿易差額主義はそのような枠組みから脱して、純粋に交換と流通の内から生まれる富の表象機能としての貨幣を重視するようになる。それゆえ、貿易差額主義においては貨幣は必ずしも金銀という実物である必要はなく紙幣という記号的存在であってよい。もっといえば、そのような実体を持たずとも結果的に貿易黒字という富の差異が確保されればよい、ということになるだろう。
これが18世紀後半になると、土地が価値を生み出すと主張する重農主義が登場してくる。だが重農主義においても、価値が生み出されるのは地主と資本家と農業労働者の間の「交換と流通」からである。重商主義の考えでは、価値が形成され増加するのは生産によってではなく、逆に交換と流通の過程において財が消費されることによってである。(フランソワ・ケネーの『経済表』は1758年の出版)
この状況が転換し始めるのが、スミスの『国富論』出版(1776年)によってである。このブログでも書いたように、すでにヒュームの『政治論集』(1752年)出版時点においてすでに労働価値説は理論化されつつあったのだが、経済思想上のインパクトとしてはやはりスミスの『国富論』出版の影響が決定的である。実際にフーコーも「アダム・スミスは、経済学的概念としての労働を発明したわけではない。それはすでにカンティヨン、ケネー、コンディヤックにも見られるからだ」と述べている。重要なのは、スミスが労働の概念を「転移」させたことだ。スミスの理論においても、「さまざまな富は依然として表象的要素として機能している。が、それらが最終的に表象するのはもはや欲望の対象ではなく、労働にほかならない。」(同上、243頁)
ここに初めて、表象の対象が〈労働〉という人間の営みに向く。スミスの理論において初めて、〈労働〉が交換のための絶対的尺度となり、生きた「人間」の営為が分析の対象となる。しかしスミスの支配労働価値説においてはまだ「商品が一定の労働を表象し、労働が一定量の商品を表象する」と考えていた点で、「表象」のエピステーメーにも属していた。これがリカードの投下労働価値説においては、価値の形成と価値の表象とが分離されることで、「表象」という思考枠組みからの完全な脱却が達成されている。
「経済学がその原理を見いだすのは、もはや表象の働きのなかにではなく、生命が死と直面するこの危険きわまりない領域の側においてである。だから経済学は、人間学的とよぶことのできる、かなり両義的なあの諸考察の領域と関係づけられるのだ。じじつ、経済は人類の生物学的特性とかかわるものであって、リカードと同じ時代にマルサスは、矯正か拘束を行なわないかぎり、つねに増加する傾向にあることを示している」(フーコー『言葉と物』276頁)。
リカードの労働価値説においては、労働は「富の表象」ではなく「生物学的行為」として捉えられるようになる。ここに19世紀近代以降の「人間」のエピステーメーが誕生する。「人間」時代のエピステーメーは、「表象」時代のエピステーメーにおける博物学・一般文法・富の分析という三つの学問分野を、それぞれ生物学、言語学、経済学というカテゴリーに置き換えたとフーコーはいう。この三つの学問分野の誕生によって、初めて分析の対象としての〈人間〉概念が登場した。
もちろんそれまでにも人間という生物は存在したし、主体としての人間について考察されることはあったのだが、人間が分析の客体として取り扱われるようになったのは、これが初めてであった。人間は「知にとっての客体であるとともに認識する主体として、その両義的な立場において登場する」。そして経済学の分野では、「労働」が研究対象の中心となったことが、「人間」時代のエピステーメーの到来を告げていたとフーコーは考えたのである。
フーコーは「人間」時代のエピステーメーにおける経済学の特徴を三つ挙げている。ひとつめは、富が「時間的連鎖の一環として組織化され集積される」ことである。とりわけリカードの投下労働価値説において価値の指標となるのは労働時間である。よって労働「時間」こそが富を構成する重要な要素となり、「経済はその実定性において、もはや相違性と同一性の同時的空間にではなく、継起的生産の時間につなぎあわされるのである」(同上、275頁)。
ふたつめは、「稀少性」が経済学の基本的な前提条件になるということだ。食料、土地、商品などあらゆる富が「稀少」であること、否、稀少であるものが「富」を成すことを前提として、経済学の思考は開始されている。言い換えれば、これは現存の富に対して人間の数が「過剰」であるということでもある。富の稀少性と人間の過剰性こそが経済学を駆動させる要件となっているのである。「事実、労働――つまり経済活動――が世界の歴史に姿をあらわしたのは、人間が土地から自然発生的に生じたものを糧とするには、あまりにも数多くなってしまった日以後のことにほかならぬ」(同上、275頁)。
みっつめは、「歴史」という概念が経済学のうちに持ち込まれるということだ。スミスもリカードも古典派経済学者はみな、年月がたつほど経済(土地)の生産性は逓減していき、将来のいずれかの時点において生産性は限界に達すると想定していた。つまり「歴史の終わり」がいずれかの時点でやってくると彼らは考えていたのである。リカードにとって人類の歴史は、窮乏の歴史であり、財の稀少性の歴史であった。人間の生命が有限なものであり、世界の財が稀少であるからこそ、生産・蓄積・消費などの経済行為が歴史的な意味をもつのであって、もしそれらが無限であれば経済学的思考に意味はない。そして、資本主義の増殖運動のもとに有限性と稀少性が無限性と過剰性を志向するという逆説が成立するのである。
「けれども、人間の基本的有限性を考えるかぎり、だれしも、人間の人間学的状況が、つねにその〈歴史〉をさらに劇的に盛りあげ、より危険のあるものとし、いってみれば、〈歴史〉をそれ自身の不可能性に近づけようとし続けていることに気づくに違いない。そうした境界にまで達した瞬間、〈歴史〉はもはや停止し、一瞬その字句のうえで身を震わせてから、永遠に不動化するよりほかなくなるのだ。」(同上、278頁)
この記述における〈歴史〉を「資本主義」と読み替えてもほとんど文意は同じである。「人間」が観察対象となることでその生物学的有限性が意識されたにもかかわらず、それと同時に加速される資本主義運動はその有限性を乗り越えて無限の価値増殖を志向する。この矛盾が「労働力商品の無理」というかたちで現われると喝破したのは、日本のマルクス経済学者・宇野弘蔵であったが、これについてはまた別の機会に述べよう。ここで確認しておきたいのは次のことだ。
「本質的なことは、経済の歴史性(生産諸形態との関係における)、人間の実存の有限性(稀少性と労働との関係における)、〈歴史〉の終焉の期日――無限の速度減少であれ、根源的な逆転であれ――それら三者が同時に姿をあらわす知の配置が19世紀のはじめに成立したということである。〈歴史〉と人間学と生成の停止は、19世紀の思考にたいしてその主要な綱目のひとつを規定する形象にしたがって、たがいに依存しあっている。」(同上、281頁)
この記述を資本主義の増殖運動という観点から読みなおせばこう言い換えられる。資本主義がもたらす無限の経済成長、労働力商品の生物学的有限性、いずれ訪れるであろう経済成長の限界と停止、この三つの要素が19世紀初頭に経済学に出揃ったのであり、この三つの相互依存的でありながら相互矛盾を孕んだ資本主義の運動が「人間」中心のエピステーメーを司っていくことになる。しかしその運動は遠からず停止するであろう、というのがフーコーの予言であった。それは経済学の終わり、資本主義の時代の終わりを意味するだけではない。「人間の終焉」じたいを意味しているのだ。このエピステーメーが消え失せるときに「人間は波打ちぎわの砂の表情のように消滅するであろう」として、フーコーはこの書を締めくくっていたのであった。
本当にかような終焉がやってくるのかは分からない。しかし、少なくとも資本主義の〈歴史〉に関していうのであれば、その終焉は必ずしもそう遠くないのかもしれない。その兆候はすでにそこここに見え始めているのだから。そのときに終焉する「人間」とはすなわち「労働力商品」としての人間なのではあるまいか。ただし、この〈歴史の終わり〉が我々にとってユートピアの到来であるのか、ディストピアの始まりであるのかは分からない。そのことについてフーコーは何も語っていない。我々は過度な希望も過度な恐怖も持たずに、この終焉のときを迎える準備を始めるべき段階に来ているのではないだろうか。それがこのブログを通じて考えてみたい主題である。
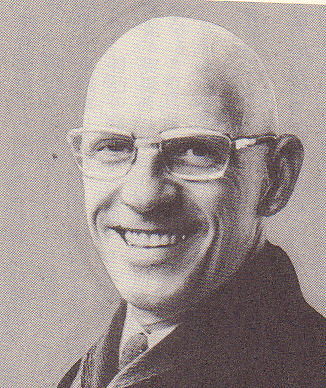
ミシェル・フーコー(1926-1984)